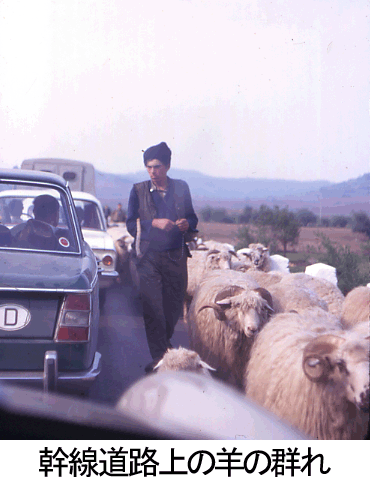ルーマニア 1969,1970
当時ルーマニアで一人歩きができたら、共産圏のどの国でも思い通りに動けると云われた。なにしろ共産圏特有の官僚主義とラテン系のいい加減さを合わせ持つお国柄なので、何一つまともに動かず、トラブルの連続であった。1969年に3回ほど出入りし、1970年には約1ヶ月滞在した。そのたびに首都ブカレストを経由して地方へ出かけるのだが、ブカレストにはまったく興味が湧かなかったので、今回は省略する。昔ブカレストは東欧のパリと云われたそうだが、見た限りでは、空き地が目立ち、道は無駄に広く、建物は宮殿風だが、人影がまばらで、放擲された町というのがピッタリな感じであった(1967年の旅日記に若干紹介してある)。

今回はクルジュ、ルムニク・ブルチャ、シビウの三つの町の旅日記である。
クルジュ(現在の都市名はクルージュ・ナポカ、ドイツ名はクラウゼンブルグ)
1969.11.22 ブカレスト(クルジュから戻って)
ルーマニアのブカレストに来た。仕事があまりなかったので、ウイーンへ帰ろうとしたら、急に仕事ができて、クルジュという町へ行った。ここはブカレストから遠く500km、オンボロ飛行機で1時間、カルパチア山脈の上を這うようにして飛んだ。ハンガリーのブダペストには400kmと近く、ブカレストの方が離れている。カルパチア山脈に囲まれている町で、戦前はハンガリー領だったとかで、人はハンガリー語とルーマニア語を喋る。ドイツ名が残っているように、かってドイツから植民がさかんであったそうで、ドイツ語を話す地域がいくつか残っていると聞いた。


1.ホモの家に泊まった話。
ここのホテルの費用は先方持ちと云う約束だったが、実際には病院のベッドで寝かされるやら、学校の宿直の先生の部屋に入れられるやらで、さんざんだった。流石に病院では病人と一緒に寝ることはなかったが、費用をケチったのか、それともホテルがなかったのか分からず仕舞い。もっともホテルがあるような町には見えなかった。
そこでの出来事、二日目の晩、ルーマニア人に招待された。全く会話が通じない家で、辞書片手に話をするのに疲れたところ、英語がうまいと云う一人の友達を呼んできた。話し込んでいる内に夜12時を過ぎてしまい、交通手段が無くなり、病院へ帰れなくなり、その友達の家に泊めてくれることになった。やれやれ助かったと思ったのがとんでもない間違いで、彼はホモで、危うくキスをされそうになった。さてはこれが話に聞くホモであるかと吃驚仰天し、そういえば、最初から態度がおかしかったと思い当たったが、さあ、その晩は心配、ベッドの下に座り込まれ、ジーッと見上げている。今にも寄って来そうだ。こっちはベッドの上で身体に毛布を巻き付け、まんじりともせず明かし、それから半日は頭がボーッとしていた。次の晩も招待したいと云われて、断るのに苦労した。ホモに会ったのは初めてだが、こりごり。
友達の流儀とやらで、互いに腕を絡めてワインを飲むというのをやらされたが、普通の流儀では全くないことを後で知った。このホモ氏よりイコンをドイツで医師をしている妻に届けて欲しいと託された。イコンは聖像板絵だが、上司への贈り物にするとかで、ドイツまで届けた。彼の奥さんはがっちりとした男勝りで、なるほどと妙に納得した。
2.今度は深刻な話。
招待してくれたルーマニア人(ホモでない方)は実はユダヤ人だった。ユダヤ人と知って、じっくり話をするのは初めて。聞くと父親も祖父も学校の同級生も全部アウシュビッツで殺された。生き残ったのは彼一人だった。助かったのは、運良く南の方に逃げられたからだそうだ。この話を彼は淡々と話してくれたが、ユダヤ人への差別は今でも根強く有るそうで、昔彼がルーマニア人の女の子と結婚しようとしたとき、相手の両親は親子の縁を切ると云ったそうである。この話を彼はしながら、このようなことを他人に話すこと自体が危険だと云った。私が日本人で、ユダヤのことを知らないから、安心して話したのだと云うことだった。彼の家にも招待されたが、そこには2才の男の子が居て、最初は女の子と思いこんだ位、可愛い男の子だった。子供が寝る前に、きれいな奥さんが裸の坊やをだいて見せてくれたが、別にドイツ人と云ってもルーマニア人といっても違いは分からない。でも子供の物心がつくころには、ユダヤ人というレッテルを貼られ、嫌な思いをするだろうことが、今からの彼の心配の種である。この人が親切な人だけに、ヨーロッパでの人種差別がよくわかり、背筋が寒くなるような想いをした。ヨーロッパを一人で廻っていると、色々なことを経験する。
もともと肉を食べるのが当たり前の地域では、人と動物はおなじ身体構造を有していることから、外観で人と動物を区別することはせず、特別の理由で人間では無いと判定した場合、直ちに当人を動物として扱ったらしい。反対も成り立つ。人の形をしていなくとも、人と認定すれば、それは人である。例として鯨がある。つまり捕鯨は殺人と云うことになる。ユダヤ人を考えていると、こんな考えが出てきた。

ルーマニアにはユダヤ人が多いそうである。ドイツからルーマニアまで逃げると、ナチスの追跡を振り切れるチャンスが多かったらしい。他の国では、ユダヤ人はいかにもユダヤ人らしいと感じることが多かったが、ルマーニアでは普通の人と変わらなかった。
ルムニク・ブルチャ
ルムニク・ブルチャの町はブカレストから北西の方向に有り、カルパチア山脈から流れでるオルト川の麓にある。ブルチャ県の県都だが、日本では知られていない町である。日本企業が建設した化学コンビナートが近くにある。1969年にも訪問しているが、技術指導を頼まれて、翌1970年に再訪し、約一ヶ月滞在した。
1970.5.1 ルムニク・ブルチャのアパート
4月29日夕方、ブカレストに着いた。商社マンと、これから訪ねる工場のルング氏が迎えに出ていてくれた。30日に車で、180kmブカレストから離れたルムニク・ブルチャ市に着いた。予想通りアパートの一室に放り込まれた。家具類がほとんどない。洗濯と自炊がやはり問題になりそうである。
1970.5.3 Zone 1 Mai, Bloc 17, RCA on 8, Rimnicu-Vilcea, Romania
ルーマニアの田舎に来て、3日目になった。メーデーのため、5月1,2,3日と休みで閉口している。今住んでいる団地は5階建て約20所帯入っている。その1階に居るが、約8帖と6帖の二部屋に台所と風呂場が付いている。以前は、ここへ来ていたアメリカ人が住んでいたとのこと。広さは十分あるが、お湯が出なかったり、電源コンセントがなかったりで、多少不便。別に風呂場がなくても死なないと諦める。人口5万人ぐらいの町だが、やはりスーパーマーケットがあって、籠に品物を入れて、出口で計算する。レジスタが壊れていて、紙に書いて計算するので、時間が掛かってしょうがない。5月1日は町の見学、メーデー祭りの筈だが、雨で中止、のんびりしている。5月2日は100km位離れたところの水力発電所と古い寺を見学、5月3日(今日)は上司のところへ呼ばれる予定。ひまでしょうがない。勉強する気もなく、毎日9時には寝ている。無理をする気はないけれど、自炊をする気も起きず、毎日レストランへ行っている。今日朝食に目玉焼きを作った。
ルムニク・ブルチャから東へいくと、次の県都クルテア・デ・アルジェシュに行き着く。この町はカルパチア山脈から流れているアルジェシュ川沿いにある、14世紀に初めて建国されたルーマニア王国(今ではワラキア公国と呼ばれている。吸血鬼ドラキュラが国王だった)の首都だった。そこに残っている修道院の聖堂と川の上流のビドラル・ダムを案内してくれた。当時は分かっていなかったが、この聖堂は世界遺産になってもおかしくない遺物だった。ルーマニアには数多くの修道院があるが、特に、国の北東部のボロネッツ修道院は外壁が絵で覆われているのが有名で、行きたかったが、チャンスは無かった。カソリックの教会からも、ロシア正教の教会からも異なる、土地に根の生えたようなルーマニア正教会の建物は何故か妖しい魅力がある。




ダムの奥に見える山並みはカルパチア山脈。
1970.5.8
やっと5月8日になった。あと2日で5月10日になる。ルーマニアでは時間が立たなくて朝7時から午後4時まで仕事をして、後は寝るまで、レストランで食事をして、何となくブラブラしているだけ。やっとお湯を沸かして風呂に入った。5月3日に買った10個の卵の内6個が残っている。どうしても30日は居ろということで、なかなか脱出できない。今日レストランで会ったイギリス人によれば、滅多なところで食事できないとのこと。彼の友達が安物のレストランで歯を折ったとのこと。この絵葉書はルムニク・ブルチアの官庁街で一番立派な通りを写したもの。この通りの向こうに2,3本通りがあるだけの町。
レストランは数軒あった。しかし、ナイフで切れる肉を出してくれるレストランは一軒しかなかった。毎晩そこへ通った。
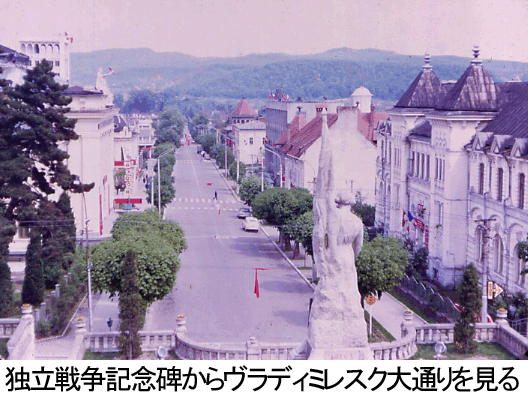
町を散歩しているうちに受胎告知教会と云う聖堂を見つけ、そこの坊さんと面識ができ、イコンを見せて貰った。A4ほどの大きさの木の板に聖像を画いたものである。例によって、聖母マリヤやキリストの磔刑などの絵が大部分だが、その中に地獄絵が何枚もあるのを発見した。日本の地獄絵と大差ない。結局宗教は違っても、人の本質には変わりが無いことが分かる。
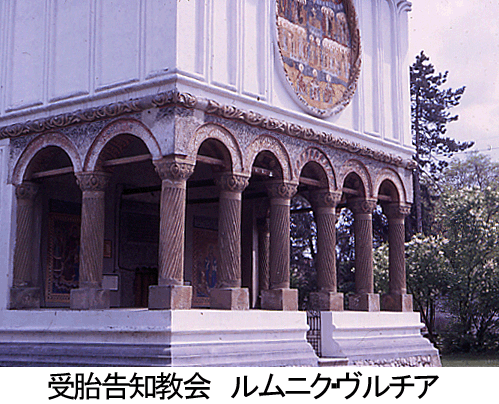
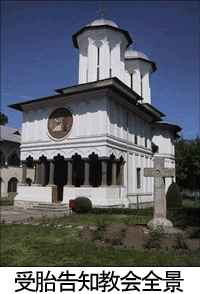

1970.5.17
ウイーンへ行く前の日の日曜日、仕事が終わってから,研究室長のユダヤ人の家に招待された。かなりルーマニアの悪口を云ったが、昨年大勢来ていたという日本人の悪口を云われ、引き分けになった。
昼間説明するために絵を描いた紙がトイレで使用済みになっていたので、文句を言ったのだが、彼らからすると、日本人も似たような無礼をはたらいたと云うことである。
今年はヨーロッパの天候が不順で、最近雨が多く、ルーマニア、ハンガリー、オーストリヤなどあちこちで洪水騒ぎが起きている。晴れると暑く、曇るとコートが必要になるなど、かなり天候が急変する。また、今居るところは少し高原に近く、しかも盆地みたいなところなので、夜は冷え込む。

このあと、5月18日にルーマニアを出て、ハンガリーを回って、また6月3日にルムニク・ブルチアへ戻った。
1970年6月13日
6月3日ブダペストからブカレストへ飛んで、迎えに来ていたルング氏に会い、そのままルムニク・ブルチャへ行った。今度のルーマニアのアパートは4階二間付きなのは結構で、テレビまである。しかも映る。ところが例に寄って、お湯がでない。始めは冷蔵庫も動いていなかった。またまた文句を付けたが、今日になるまで、何時お湯が出るのか分からない。給水は時間制だそうだけれど、時間割が分からない。それどころか、2、3日前はまるまる二日間普通の水も止まってしまった。後で聞くと水源が切り替わったのだそうだけれど、こっちには解らないから、二日間は顔も洗わなかった。勿論6月3日以来風呂にも入っていない。不潔な話で、流石に匂ってきたから、水で拭いている。
ルムニク・ブルチャへの道の途中で、ロマの人々(昔風に云えばジプシー)とすれ違った。馬車を連ね、ゆうゆうと移動している。彼らには国境というものはない。勿論交通法規にも関係ないから、路上で止まり、街道を占領していることも起こりうる。自由気ままが羨ましいとも云える。ナチスのせいで、ロマの人たちも随分減ったが、それでもルーマニアにはまだは多くのロマの人がいるそうである。

それから、4,5日前、部屋で整理をしていたら、いきなり、部屋を合い鍵で開けて、掃除婦が一人の男をつれて入ってきて、チェコとルーマニアのフットボールの試合をテレビで見たいので、部屋に居させてくれと来た。呆れて失礼と思わないのかと云ったら、黙っていて、そのうち見せてくれるのか、くれないのかと来た。断ったけど、プライバシーなんか有ったものではない。後で、人に話をしたら、そんなときにはたたき出して構わないと云っていたから、プライバシーは多分あるのだろう。とにかく住むのには大変である。その代わり、仕事先のコンビナートの人々は彼らなりに一生懸命にしてくれる。今、フットボールの世界選手権をメキシコでやっていて、ルーマニアも参加しているので、そのテレビ中継で皆が熱狂していた。時差の関係で、放映は夜の12時からである。バラバラでテレビを見るのはつまらないから、皆で集まろうということになり、テレビのある家に行った。コンビナートの人以外に何人かの女性も参加し、コニャックとコーヒーとパンを囓りながら、テレビを夜2時まで見て、それでお終いかと思ったら、それから、テープレコーダーを鳴らし、ダンスを始めた。深夜3時まで付き合ったが、我慢ができなくなり引き上げた。連中は朝6時まで続けていたらしい。なお、7時から仕事である。タフのように見えるけど、流石にその日は皆フラフラしていたから、そうでもないらしい。連中の平均年齢は25才だから、その位は普通だろう。それで、7時から仕事をして、3時に終わって、家に引き上げる。そして、夕方6時から8時ごろになると、町の中心に皆集まってきて、何をするでもなく、わいわい雑談をして、引き上げてゆく。何もないところなので、町の中心の通りが社交場になっているらしい。他の町でもそうだから、ルーマニアでの習慣かも知れない。けったいなものである。
室長の家には何度も招待されたが、彼はユダヤ人である。奥さんはハンガリー人、奥さんの両親はハンガリー人とルーマニア人。その両親はフランス人とドイツ人とかで、奥さんの国籍はハンガリー人、市民権はルーマニアとかで、ヨーロッパの人種は込み入っている。室長はドイツ語、英語、ロシア語と話し、フランス語、イタリヤ語も分かる。しかも奥さんとはハンガリー語、研究所ではルーマニア語を話している。聞くところによると、ユダヤ人は小さい頃から語学を両親に教育されるのだそうだが、一般のルーマニア人の90%はルーマニア語しか知らないそうである。


今ルーマニアは洪水で、大変である。今居るところは心配ないらしいが、ルーマニアの北の方とハンガリーの一部では初めての洪水らしい。聞くと、第2次大戦のときの被害より大きいと言う。今住んでいるところでも、川の水位がかなり高いそうで、皆で水を見ながら、何か言っている。ここの気候は盆地のせいか暑いようだけど、今年は涼しいそうである。日中は30℃近いが、いつもは35℃ぐらいあるそうである。そして、一日一回は夕立が来る。そして、夜は幾分涼しくなる。
1970.6.20 (フランクフルト、ドイツでのメモ)
6月3日にルーマニアのルムニク・ブルチャへ入って、そのまま6月18日の午前中までいた。洪水の心配はなかったが、最後まで水に悩まされた。お湯も水も出ないので、この間、風呂に入れなかったわけ。6月18日ルムニク・ブルチャを出るとき、猛烈な下痢に襲われた。食べたものはラーメンと卵(これがいけなかったのかも知れない。一週間前のやつ)それと、古いパン、このうちどれかが原因。それで、ともかく19日ブカレストで高いホテルに泊まり、風呂に入ろうとしたが、今度は風呂があっても、入れないということになり、往生した。今日20日ようやくよくなった。そうそう、ルーマニアではバラが綺麗だった。洋風の古い家にバラが絡んでいるのは風情がある。
下痢になった原因はコンデンスミルクだった。ウイーンから差し入れ品だったが、うっかり生水で溶いたのがいけなかったらしい。このあと、ドイツ、チェコと廻り、7月18日に羽田に帰り着いた。
シビウ(ドイツ名はヘルマンシュタット)
シビウはルムニク・ブルチャから北へ、アパラチャ山脈を越えたところにある、ドイツ人が12世紀に造った町である。



1970.5.10(月)
早めに仕事を終えて、慰問に来てくれた商社の人と100kmばかり離れた古都シビウという町へドライブした。帰り道に運転をさせて貰い、約80km位の距離を大型のフォルクスワーゲンで乗り回した。シビウという町はカルパチア山脈の反対側にあるので、運転免許を取ってから、初運転はカルパチア山脈越えということになった。思ったより,まともな運転ができた。これに味を占めて,レンタカーを借りようと思ったら,ルーマニアの片田舎にはそんなシステムはなかった。
日本で運転免許証を取ったばかりで、ルーマニアに来たので、このドライブが最初だった。同乗者がハラハラしているのが分かり、申し訳なかった。しかし羊に囲まれながらの運転は乙なものである。と云うわけで、シビウの町の印象はほとんど残っておらず、よくある古都の一つと思った程度。