スペインとポルトガル
スペイン
スペインは好きだ。仕事で、遊びで、何度も行っているが、何となく魅力のある国である。人々は素朴で、少々野卑で、イタリア人のように意図的に騙そうとはしない。でも人懐っこい。1972年のマドリッド、マラガ、グラナダ旅行を中心に、1973年のセゴビア、ビルバオ、1974年のバルセローナの旅行記を載せる。

バレンシア
スペインを初めて訪れたのは、実は1969年である。ドイツからバレンシアへ行く予定が、飛行機の乗り継ぎに失敗して、滞在時間が削られ、町を全く見ていない。従って、記録もないが、パエリアを食べたことは覚えている。
1969.4.2 バレンシア
3月30日にドイツのジュッセルドルフへ着くと、すぐスペイン東海岸のバレンシアへ行けと言うことで、31日に立ったが、急いだせいで、切符の手配が間に合わず、ジュッセルドルフ→フランクフルト→ジュネーブ→マドリッド→バレンシアと飛びながら、切符を買い足して行くつもりが、ついに途中で間に合わなくなり、スイスのジュネーブで予定の飛行機が私のトランクを積み込んだものの、私を残して先に行ってしまった。仕方なくジュネーブで泊まり、翌朝レマン湖まで散歩してから、空港に戻り、マドリッド行きの便に乗った。マドリッドの空港では、流石にスペイン語はまったく分からず、やっとの思いで乗り継ぎ便を探し、バレンシアへ着いた。あとは順調で、昼間からワインを飲んで、エビと米の炊き込み料理(つまりパエリヤ)などでいい機嫌だったが、残念ながら、ホテルの外に出る時間は全く残っていなかった。


残っているメモに書かれていることとは反対に、実際には真っ青になって困り果てた。だだっ広いジュネーブ空港の中を駆け抜けてゲートにたどり着いたときには既に飛行機は滑走路で、どうしようもなかった(2年ほど後で、コペンハーゲンの空港で、やはり遅れたとき、同じように遅れた乗客が滑走路に飛び出し、飛行機の前に仁王立ちになり、手を降って止め、タラップを降ろさせ乗りこみ、便乗してこちらも乗り込めたことがあったけれども、ジュネーブではそんな蛮勇も機転もきかなかった。勿論現代では論外の話しである)。そのときどうやって、客先に「遅れる」と連絡を入れ、ホテルを確保したか覚えていない。
マドリッド
当時欧州行きの航空券なら欧州内をあちこち廻ることができたので、日本からのチケットを利用して、どこか遠いところへと探し、夏休みにスペインに行くことを決めた。当時日本ではまだ夏休みが根付いていなかったように記憶しているが、欧州では夏休みは義務に近い。早速その習慣に便乗することにしたものの、流石に現地風に2,3週間とは行かず、一週間前後の休みが精一杯であった。毎日が曇りか小雨のドイツを飛び立ち、マドリッドに着くとまだ明るい。空港では、降ろされた旅行鞄を自分たちで運び、税関でかなりうるさいチェックを受けた。ああ、フランコ政権の国に来たと感じた(スペインが王国に戻るのは、それから3年後のことである)。右翼の国と左翼の国での扱いは似たようなものだ。空港から都心へのタクシーの中から、オレンジ色の夕日が輝いているのが見えた。マドリッドは秋田県大館市とほぼ同じ緯度にあるが、サマータイムもあって、この時期の日没はかなり遅い。

1972.7.6 マドリッド ホテルフェニックス
出発は夕方なので、ゆっくり準備する。昼頃からまた雨が降り始める。飛行機はジュッセルドルフを予定より遅れて出発する。マドリッドに午後7時半頃着く。太陽がギラギラしていて、日本を思い出す。町の中が雑然としているところまで似ている。夜フラメンコを見ようと云うので、10時頃からタクシーでフラメンコを見せるレストラン(タブラオ「エル・コラル・デ・ラ・パチェカ」、踊りが主だが料理も出る店)に行く。空いていたが、迫力のある踊りに圧倒されてしまう。夜12時にホテルに帰る。

タブラオは、板張りの踊り場の周りに観客席がある拵えになっている。フラメンコでは華やかな女の踊りがよく知られているが、圧倒的なのは男の踊りである。内にある情熱を抑えて、身悶えするようなステップがゾクゾクとする。40年前のこのタブラオは今でも営業しているらしい。
1972.7.7 マドリッド→トレモリノス(マラガ)
午前10時半にホテルフェニックスを出て、まずスペイン広場に行く。写真を写してブラブラ歩く。やがて王宮が見える。ちょっと中庭に入っただけで、建物の中は見ない。衛兵が面白い帽子を被っている。日向はとても暑い。そこから歩いてマヨール広場に入る。広場の周囲には沢山店がある。ペンダントなど土産物を買う。レストランに入ったけど、フルコースでないと駄目といわれて、断られる。細い路地を沢山歩いてプラド美術館の方に行く。途中立ち食いスタンドに寄って、いかの天ぷらとコーラで昼食、少し生臭かったが、割に美味しい。又歩いて疲れてしまったので、タクシーに乗る。プラド美術館の裸のマヤの肌の色が素晴らしい。ゆっくり見たかったが、マラガ行きの飛行機の時間があるので、ホテルに戻り、荷物を持ってマドリッド空港に行く。飛行機の出発は3時間遅れた。


スペイン広場は代表的な観光スポットだが、要はセルバンテスの記念碑があるということ。
彼のモニュメントの前にドン・キホーテとサンチョ・パンサの像が可愛らしく置かれている。その前で写真を撮るのが定番になっている。


王宮は、ルーブルとかバチカンのサンピエトロ寺院のように、四角な建物の両袖が伸びて中庭を作っている構造になっている。横に被っているような衛兵の帽子、多分三角帽子というのだろうが、初めて見ると奇異に感じる。

長方形の広場の周囲をぎっしり建物で取り囲まれているマヨール広場は、周囲から切り離された独立の空間になっている。ちょっと気取りすぎの広場だった。

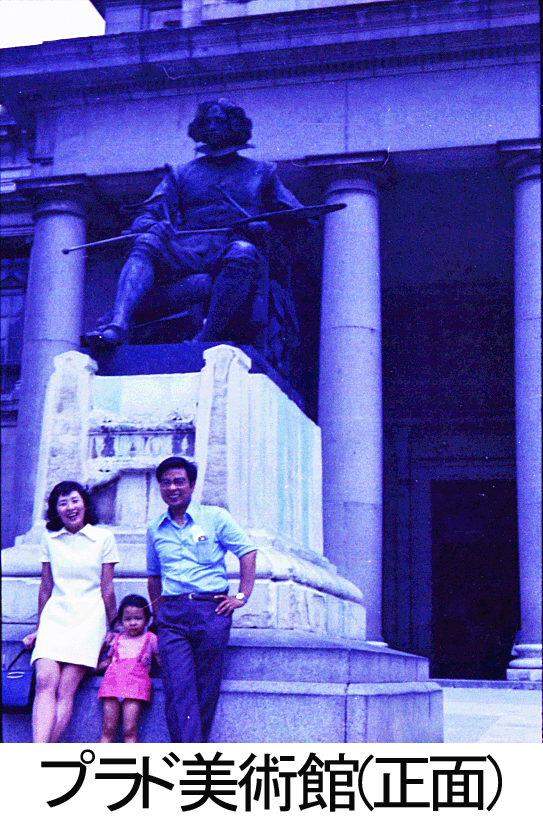
プラド美術館と云えば、ゴヤのマヤ(裸と着衣の)の絵もさることながら、地下にあった「黒い絵」が恐ろしく、強烈な印象を残した。
トレモリノス(マラガ)
そもそも、スペイン行きの目的は海水浴だったので、マドリッドから地中海を目指してマラガに飛んだ。マラゲーニャで有名なマラガの町を中心に、スペイン南部のアンダルシアに広がる海岸線はコスタ・デル・ソル(太陽の海岸)と呼ばれる観光地域である。マラガの一部と思って、ホテルを予約したトレモリノスの町はマラガ空港を挟んで、マラガ市街地と反対の西側にあった。出発前の勉強不足で、トレモリノスは観光のために開発されたリゾートタウンであって、マラガとは全く別の町とは知らなかった。


1972.7.7 トレモリノス
マラガの空港に夜8時過ぎに着く。すごく涼しい。天気も悪い。明日からこんなだったらと心配になる。タクシーでトレモリノスに行く。ホテルのフロントへ行ったら、第3棟の建物へ行けという。鍵を渡すから、あとは勝手に行けということらしい。どうもホテルではなく、貸し別荘みたいなものらしい。戸惑ってしまう。タクシーの運ちゃんが9階の部屋まで付いて行ってくれて、やっと落ちつく。今度は食事の心配、冷蔵庫から食器まで何でも揃っていたが、食料は何も無い。やはりレストランを探さねばと、別荘団地を通り抜けて食堂のようなところへ行く。外で食事をしたら寒い位、雨までポツポツしてくる。

あらためて、欧州における夏休みの意義を知ることになった。日照の少ない欧州にとって、日光浴は必須である。2週間から一ヶ月程度の休みを取り、ひたすら日を浴びる。滞在費を倹約するため、外食はしない。よって自炊ができる貸し別荘しかない。2,3日滞在すると言ったら、何をしに来たと怪訝な顔付きをされた。当然である。天候の悪いのが意外であった。コスタ・デル・ソルは年間300日以上晴天と聞いていたのだが。
1972.7.8
9時頃まで寝ていて、午前中団地内のスーパーでサンダルやら食料品などを買う。朝昼兼用の食事をして、海に出かける。デッキチェアを二つ借りてのんびりひっくり返る。目の前は地中海。日本の海と変わっているところは何もないが、この海の向こうはアフリカかと思ったり、きれいな海を見ているとスペインにいるのだと実感が湧く。水はすごく冷たくて、急に深くなるし、あまり皆泳いでいない。

後はプールに切り替える。
1972.7.9
朝からプール。芝生のデッキチェアで寝ている。昨日より暑い。日に当たると痛いぐらい。それでも風は冷たくて、子供達はプールから出ては寒い寒いと大騒ぎ。2時頃引き上げて、1時間ぐらい昼寝をして、今度は海の近くのレストランでヒラメのムニエルとイカ天。おいしい。夕方の海辺をブラブラしたりする。
気温は42度。こんな高い気温は初めての体験、以後もなし。しかし、水から上がって、日陰に入ると身震いするほど寒い。湿度が低く、急激に気化熱を奪われるためである。暑さは気温で決まるものではないと思った。
アルハンブラ(グラナダ)
1972.7.10アルハンブラ(グラナダ)
アルハンブラを見るために、レンタカーでマラガからグラナダへ行く。アルハンブラは、スペインに約800年間続いたイスラム王朝の最後の砦である。かなり破損しているものの、それでもイスラムの建築美を味わうことができる。
トレモリノスでレンタカーに試乗してみると、ブレーキが効かない。冗談ではない。何台かテストして、大丈夫そうな車を選ぶ。スペイン国産車であるセアットだが、イタリヤのフィアット傘下と聞いた(今は違う)。マラガから山道を登り、あとは荒涼たる台地を、同じ方向に向かう車と抜きつ抜かれつ、ひたすら飛ばした。あとで、相手から、そんな車でついてくるとは感心と妙なほめ方をされた。結果的にはよく走ってくれた車だった。


朝10時頃にマラガを出る。レンタカーはセアット、赤い可愛らしい車で、マラガの町をグルグル回ってやっとグラナダ行きの道に出る。山の尾根を走っている。途中白っぽい家がところどころに見られる。山を越えると今度は西部劇に出てきそうな景色の山が(すごく大きく、変わった格好をしている)次から次へと出てきて、ちっとも退屈しない。やがてオリーブが規則正しく植えられている畑が見えてくる。しばらく走って、ロハの町が下に見える。この辺から道が良くなる。グラナダに近づくと、真正面のはるか高くシエラネヴァダの白い雪を被った山々が見えてくる。
アメリカのカリフォルニア州にもシエラネバダがあるが、スペインのシエラネバダ山脈が本家である。3000メートル級の山々が並び、万年雪が残っている。この辺の景観はまさしく西部劇そのもの。
グラナダの町に入り、ホテルを探しているうちにアルハンブラに着いてしまった。最初に夏用の王宮とも知らず、ヘネラリーフェ離宮に行く。糸杉の柔らかい感じ、水をふんだんに使ってある庭、回廊の窓から眺めるジプシーの洞穴の住まい、言葉にならないぐらい素晴らしい。

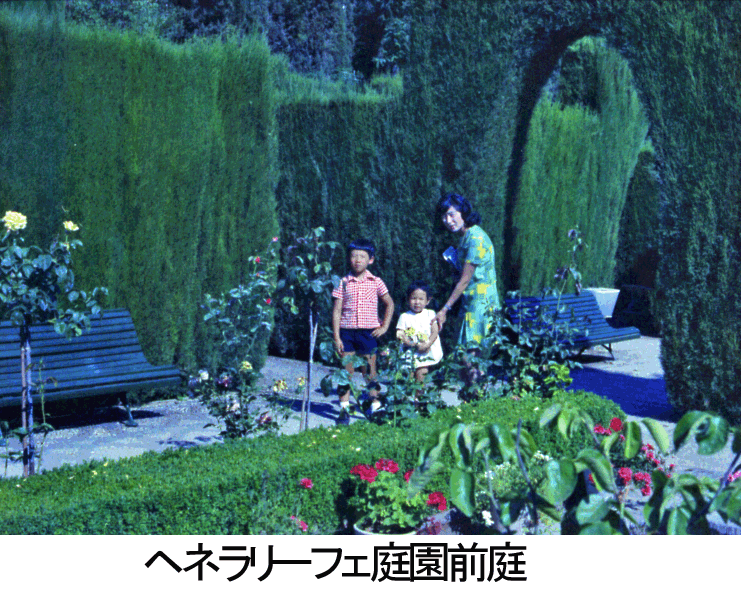



ヘネラリーフェ離宮はアルハンブラ宮殿の北隣に立つ丘の上にある庭園である。緑の高い生け垣、咲き乱れる花々、きらめく噴水など、思わず立ち止まり、息を飲む美しさであった。順に新庭園、庭園、パビリオンで囲まれたアセキアの中庭と続く。パビリオンから外を見れば、アルハンブラ宮殿やアルバイシン(ロマの住居地区)が目に入る。
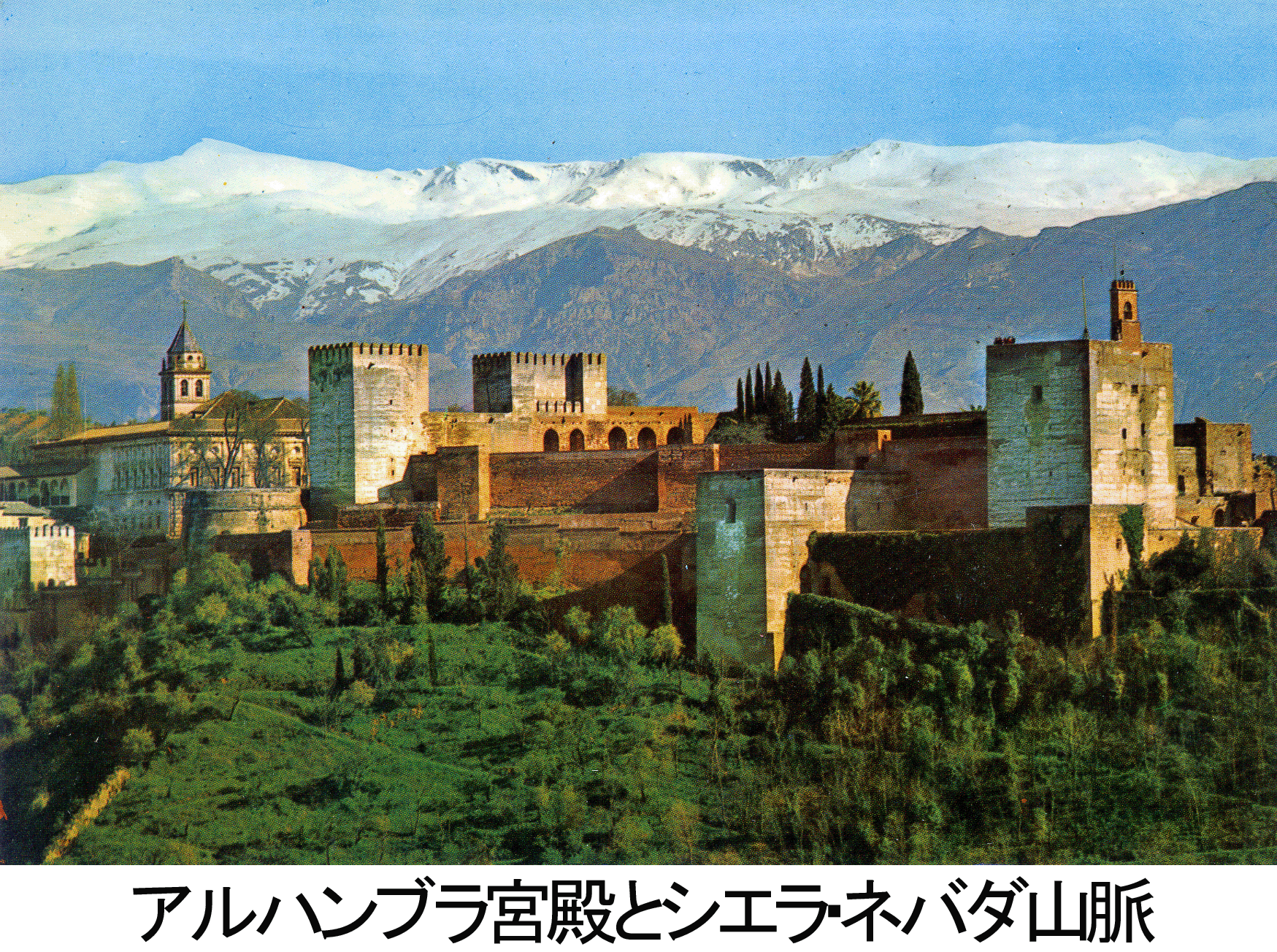

いったんヘネラリーフェ離宮から外へ出て、アルハンブラ宮殿に行く。建物の内装に目を奪われる。案内書と首っ引きで1部屋1部屋見て回る。クタクタに疲れていたが、ここを見なければと思う。見ているうちは疲れたのも忘れてしまっていたけれども、見終わってベンチに腰掛けたとたん、動くのが嫌になった。しばらく座っている。

アルハンブラは、グラナダ市の中央に突き出ている丘の上に作られた城塞である。宮殿として残っている部分はごく一部だが、中庭を囲む建物の連なりは華麗で優雅としか形容できない。裁きの門から、ガランとして不格好なカルロス五世宮殿(キリスト教国になってから作られた)を通り抜けて、メスアールの間、アラヤネスの中庭、大使の間、ライオンの中庭、貴婦人の塔と、疲れるのも忘れて、見て歩いた。イスラム装飾が印象的であった。




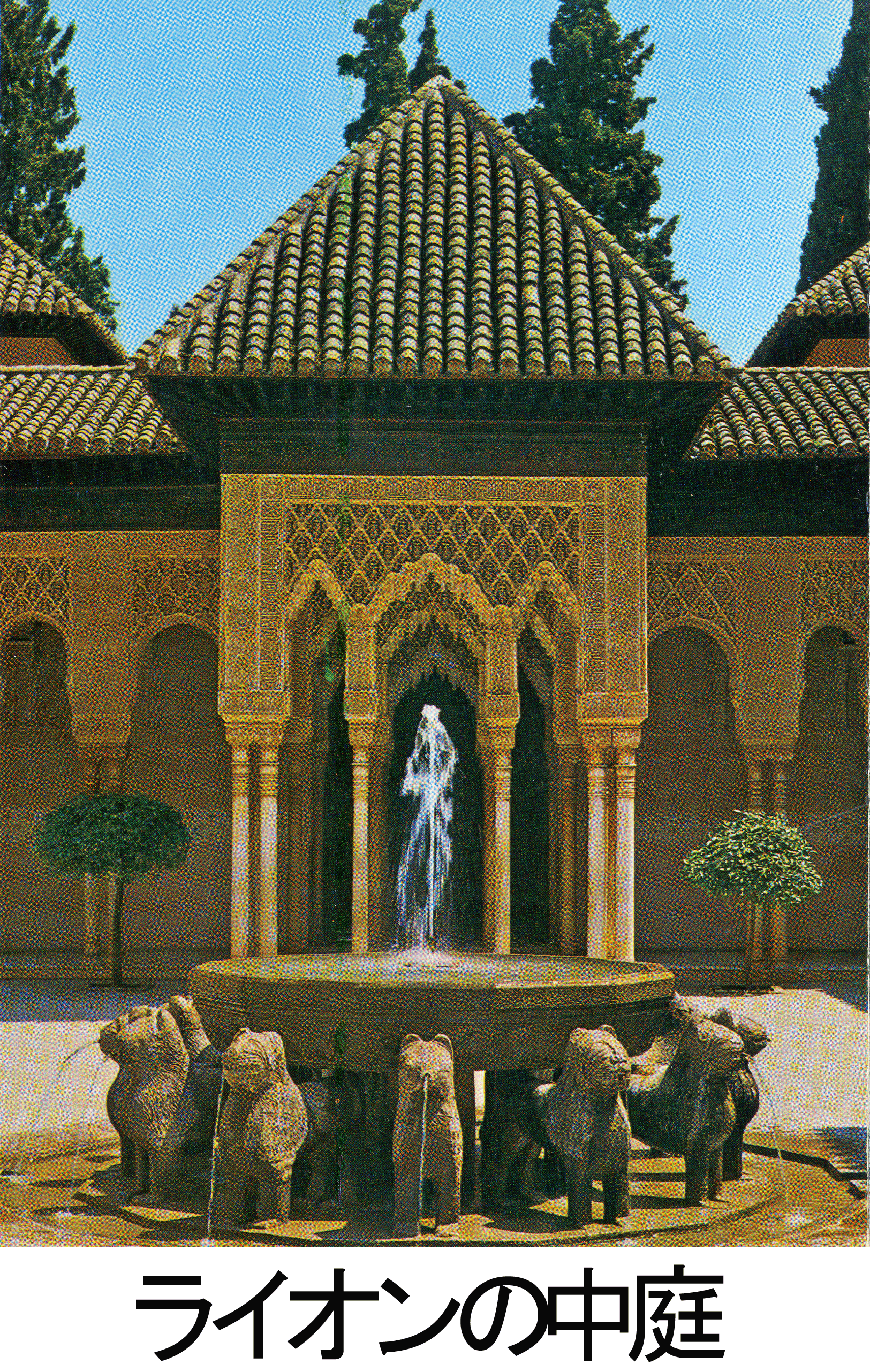

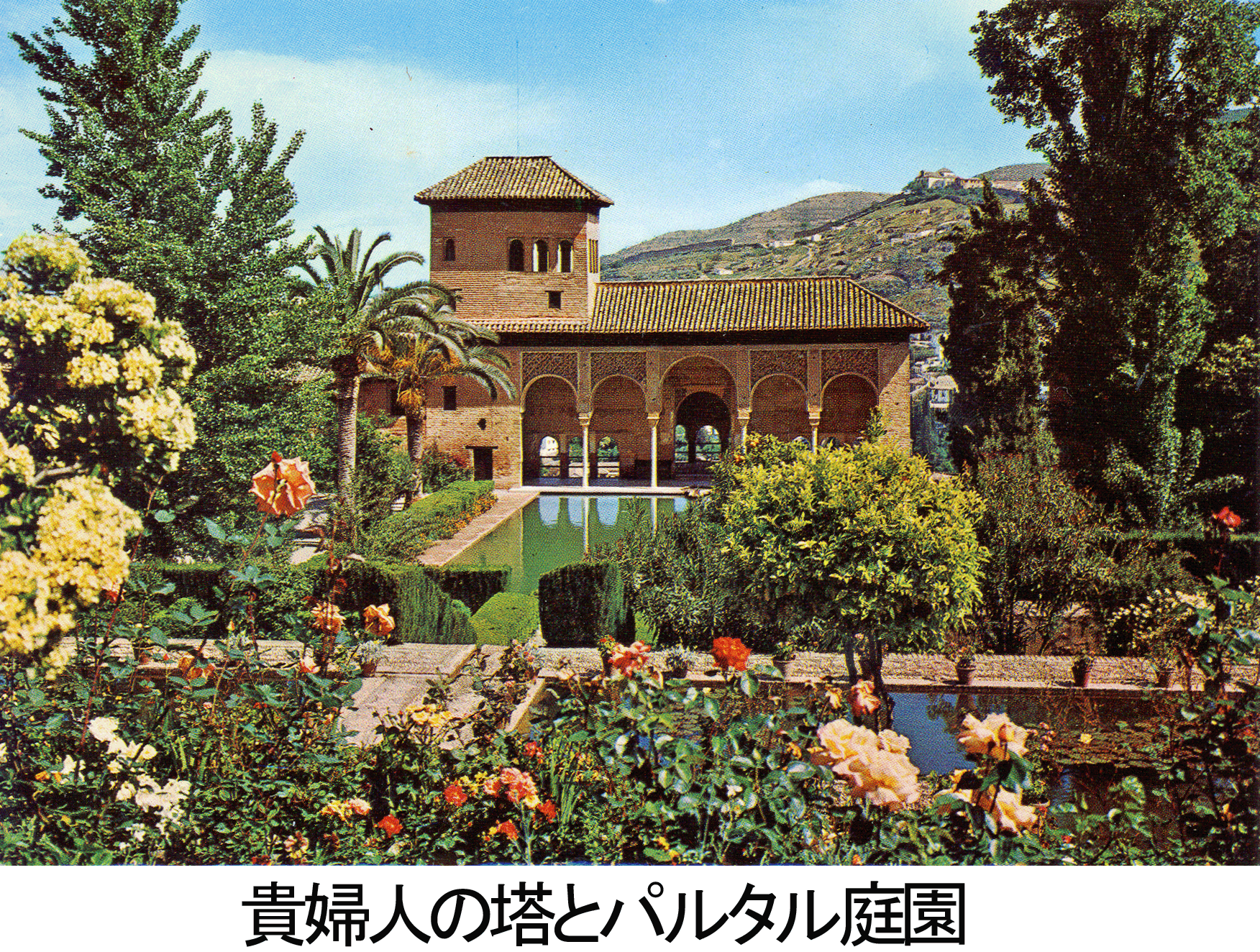

疲れてグラナダの町を見る気も起きない。ホテルを探しに行く。予約してあったホテルは一流のホテルだったが、家族が泊まれるスィーツがない。他のホテルに変える。ちょっとひどい部屋。レストランに食事に行く。サングリア、鱒がとてもおいしかった。
ホテルを急に変えたのでやむを得なかったが、廊下の外は岩壁であり、トカゲが這っていた。でもサングリアは美味しかった。赤ワインとレモンネードにシェリーを加え、小さく切った桃を落とし込んで、冷やして飲む。
1972.7.11
10時頃ジプシーの洞穴に行こうと思ったが、車で行けないので、やめた。又マラガへと走る。
アルハンブラの向かい側の斜面のアルバイシン地区に、洞穴を住居にしているロマが居ると聞いて、車で向かったが、狭い曲がりくねった道に迷い、やむなく割愛。来たときと同じルートでマラガに戻った。このあと、マドリッド経由でポルトガルのリスボンへ。
リスボン(ポルトガル)
1972.7.11
マラガの空港からマドリッドに飛行機が遅れて、乗り継ぎ時間ぎりぎりに着く。ところが後続の飛行機がさらに3時間遅れた。リスボンのホテルに着いたら、夜11時半。レストランも閉まって夕食もたべられない。やむを得ず、ホテルサービスでサンドウイッチを頼む。
スペインのマラガからマドリッドを乗り継いで、ポルトガルのリスボンへ向かったが、イベリア航空が遅れ、夕刻には着くはずのところ、深夜になってしまった。リスボン空港に着陸する直前の、街灯で照らされた街並みの美しさが心に残った。そのせいか、スペインと違って、ゆったりとした雰囲気が心地よく、親近感を覚えた。
1972.7.12 リスボン
市内を見物。まずジェロニモ修道院。タクシーでグルグル回る。細い路地に急に電車が現れ、びっくりさせられる。坂道を上がったり、下がったりするので、気分が悪くなる。魚のレストランに行って、大きなエビを食べる。あまりおいしくない。小さいエビを、家に持ち帰れるように、包んでもらった。
実質半日しか時間がなく、ジェロニモ修道院、エンリケ航海王子の発見のモニュメント、ベレンの塔、サンジョルジュ城等を廻り、昼食を食べたら、時間切れになった。大きなエビを頼んだが、持て余して、食べ残したら、給仕が勿体ながって、食べろ食べろとうるさかった。



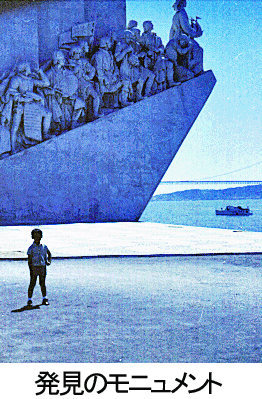


1972.7.13家に戻って
頭がフラフラ、胸がムカムカ。
短時間の滞在であったからこそ、今でもリスボンの印象は鮮明に残ってる。民謡ファドを聞き損じたのは残念だった。
スペイン
セゴビア
マドリッドの北90km位に位置するセゴビアという町に出張した。古い町で、ローマ時代の水道橋が町のど真ん中、旧市街と新市街の境界に残っている。長さ730m、高さ30m、幅2.5mの、セメント類を使わず、石のブロックを組み上げただけの橋だが、2000年立った現代でもびくともしていない。イスタンブールの水道橋より臨場感がある。スペインでは、セゴビアやグラナダのような古い町はもともと城塞であって、河の合流地点や河の湾曲部にある三角形の台地の上に立てられていることが多い。そのような城塞で、遠い水源から水を引かなければならないとき、台地の上の町へと水道橋をかけることになる。それにしても、驚くべき古代の技術である。
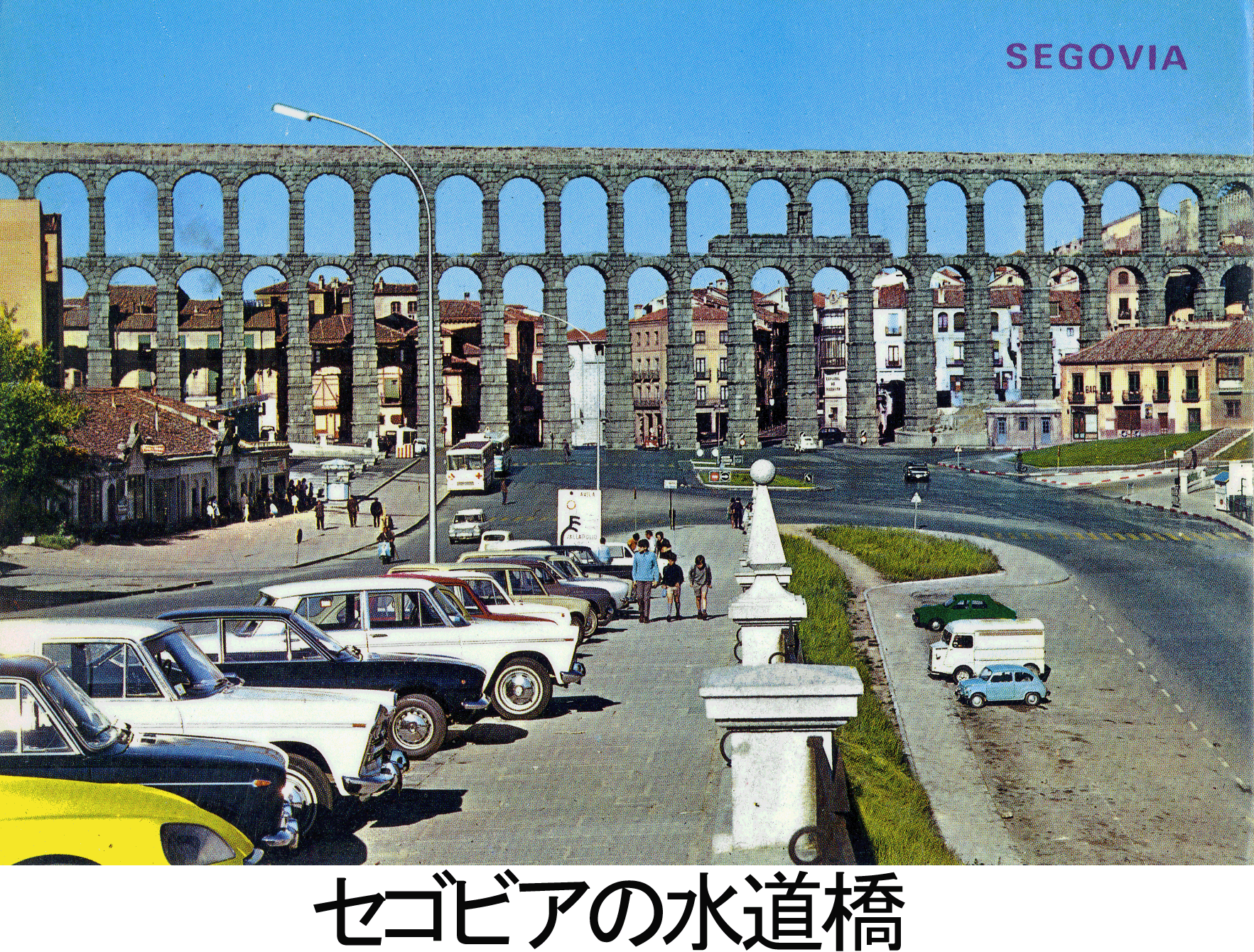
1974.1.7〜1.9
朝暗い内から、ホテルを出る。雨が降っている。外のレストランで朝食をとる。何人かが立ったまま朝食を食べているが、合間にぐいとブランディを引っかけているのには、びっくりする。こちらでは普通のことで、労働者の景気付けのためだそうだ。仕事先はセゴビア郊外の工場だが、仕事が思うようには進まず、夜遅く帰ってくる。疲れて、何もする気が起きない。
それでも、名物料理には有り付いた。乳飲み子豚の丸焼きである。水道橋のすぐ脇にある「カンディドの店」に行った。店のショウウィンドウに子豚の頭が勢揃いしていた。ユーモラスでもあり、残酷でもある。面白いことに、子豚を取り分けるのに、ナイフを使わず、皿のヘリでたたき割る。発祥の地はここセゴビアだが、マドリッドでも食べることができる。スペインを長い間支配していた、豚を食べないイスラム教徒を意識した料理ともいわれている。味は鶏肉とあまり変わらないように感じた。

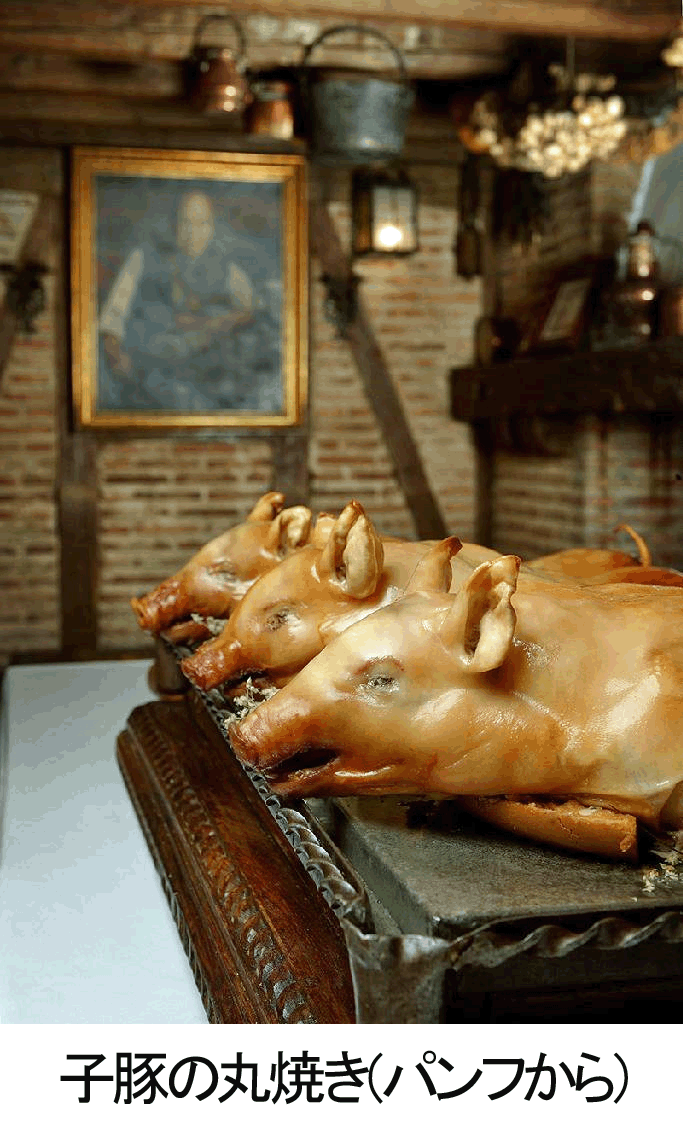

1974.1.16,17
スペインの雨期は冬である。滞在中ずーっと雨だった。セゴビアは暗い、寒い、冷たいという印象を与える。夏来れば違うのだろうが。
例によって、時間が取れず、観光はできなかったが、遠くにチラッとお城が見えた。白雪姫のお城のモデルとされているお城だそうで、整った形をしている。

ビルバオ
ビルバオはマドリッドから北へ400km、イベリア半島の北部に位置し、ビスケー湾(大西洋)に向けて開かれている町である。スペインでの有数の工業都市であり、貿易港でもあると聞いているが、見たところ、ごく普通の街であった。つまり、スペインの他の都市のように、気候の厳しい町ではないということである。でも別の面から少し違う印象を与える。バスクの町であるという無言の押しつけを感じるのだ。フランスからの海岸線が繋がるスペイン北部にはバスク人が住んでいるが、独自のバスク語を話し、人種的にもスペイン人と異なるらしい。なんでも先史時代のクロマニオン人の直系の子孫との噂が残っているとか。ケルト人やローマ人より古いことになる。現在でも独立を目指すテロ組織が存在し、絶えず問題を起こしている。しかし訪問したときはフランコ政権の締め付けがまだ厳しく、不穏なものは何も感じなかった。
1974.1.10 セゴビアからビルバオへ
セゴビアから車でビルバオに向かった。途中、ブルゴスの町を通り抜けた。町中の河を渡るとき、向かいに見えた大聖堂が印象的である。ここには伝説の英雄エル・シッドの墓がある。たしか「エル・シッド」という映画があった。


1974.4.11 ビルバオ
「アキー、バスク(ここはバスク)」というラジオの音で目が覚めた。バスク地方に居ることを実感する。表に出る。無骨な男達がベレー帽を被っている。ベレー帽の発祥地であることにも気づく。悪気はないが、無愛想である。なんだか職人の街のような気がする。
1974.1.12
アングラスを食べた。前菜だが、美味しくて、お代わりを頼み、笑われた。アングラスはウナギの稚魚(シラスウナギ)。小さな土鍋にニンニクと唐辛子とオリーブ油を入れ、炒める。熱々になったところに、5〜10cmのアングラスを放り込み、木のふたをして、そのまま4,5分置き、木のスプーンで食べる。日本そばの感触と変わらない。美味であった。

このウナギの稚魚は近くのビスケー湾で取れるらしい。当時でも高価だったが、今はもっと値が張るかも知れない。私の3大美味の一つだが、滅多に食べられない。代わりにエビとイカを使っても結構いける。我が家のお客さんにも好評だった。
ビルバオの街は観光には向いていない。今でこそ、グッケンハイム美術館ができたそうだが、当時はこれという名所はなかった。絵葉書には、離れた山中のお城と海への河口に掛かっているビスカヤ橋が載っているが、町中の風景はない。ビスカヤ橋は吊ったゴンドラを移動させて、人、車を運ぶ、珍しい橋である。


アルタミラ洞窟
日曜日にアルタミラ洞窟へ案内してもらった。1879年に発見された旧石器時代の洞窟である。1万年から2万年位前に画かれた壁画で有名である。
1974.1.13 サンティリヤーナ・デル・マル
日曜日ということで、アルタミラに案内してもらう。ビルバオから西へ、サンタンデルの町を通り過ぎ、サンティリヤーナ・デル・マルという田舎町に着き、宿屋で昼食をとる。ワインは美味しかった。
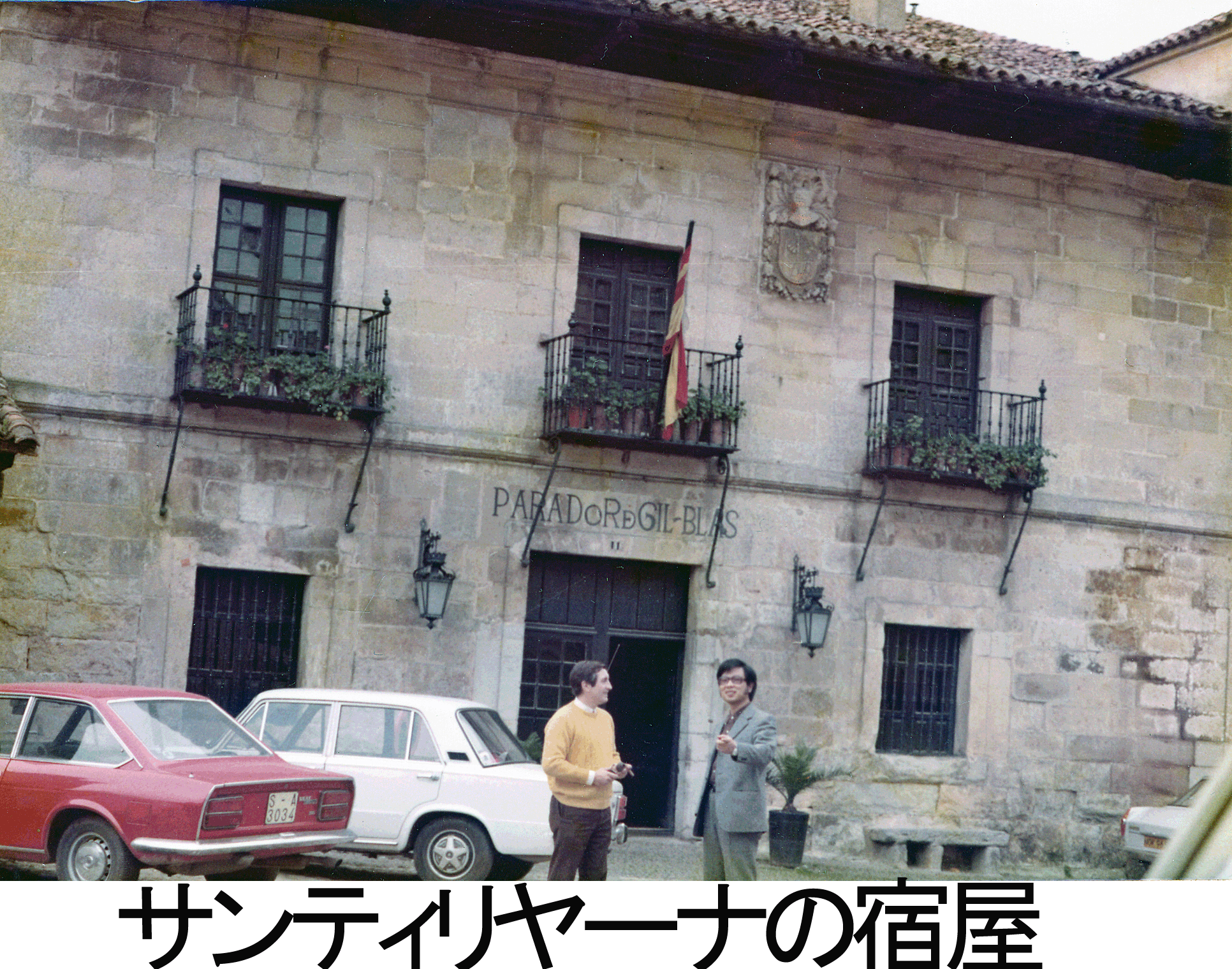

アルタミラの洞窟に行く。

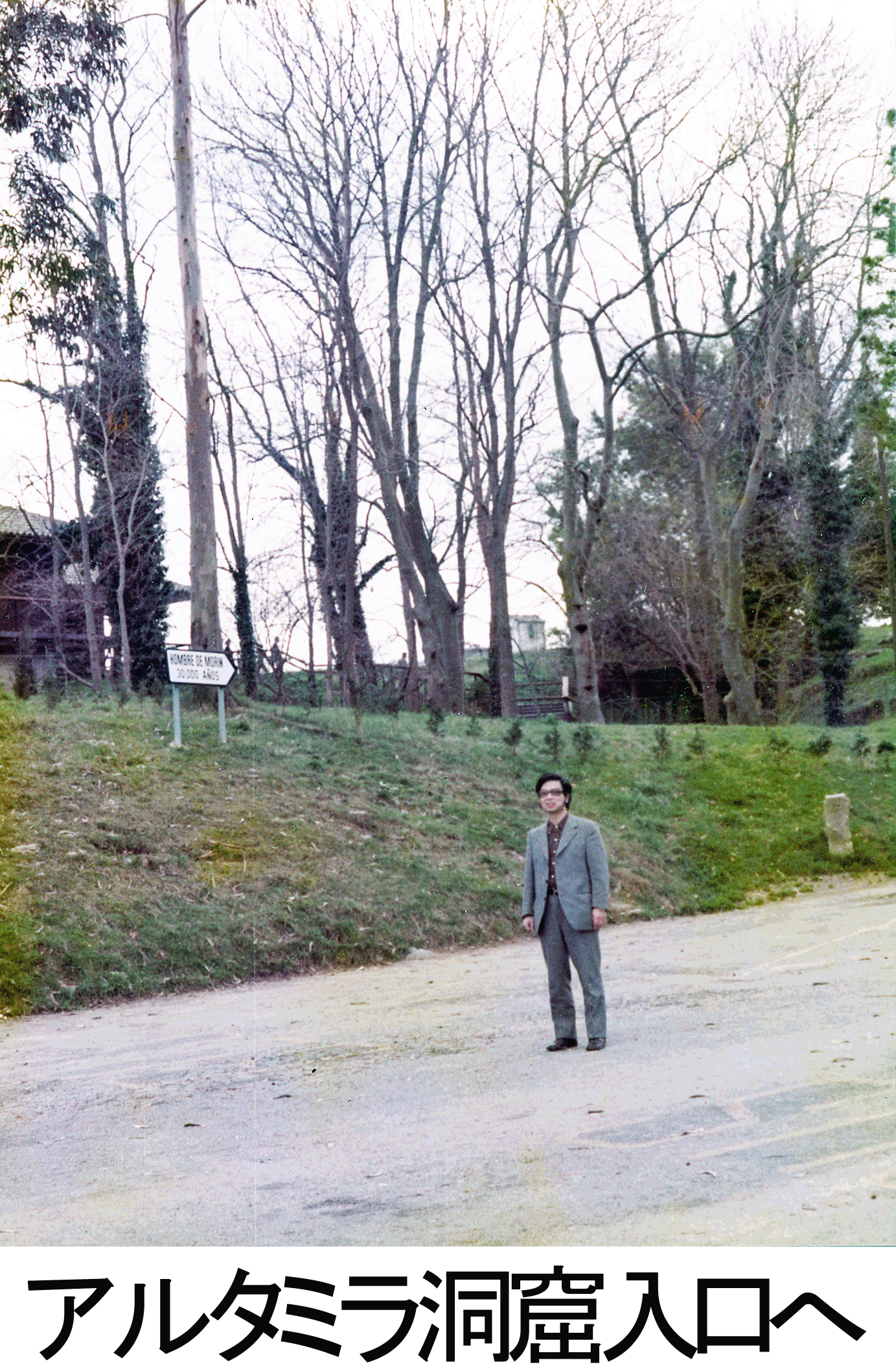
何の変哲もない丘陵がいくつも広がっている。その一つの丘の上に小さな建物が有り、その中に3万年前の人と称する、わけの分からない物を封じ込んであるガラスのような置物がある。そこを通り過ぎて裏手に出ると、横穴がある。洞窟と聞いていたから、多少大きな洞穴を想像していたが、入口は人ひとり入れる位の穴でしかない。中も広くはない。左右への広がりはあるが、高さが2mもない。しかも足元はでこぼこで、歩くのに神経を使う。下ばかり見て歩いていたら、「ここ」と指さされた方向は天井であった。目の上に、なにやら赤っぽい色が見えた。しばらくして、それが、天井の出っ張りを利用して画かれたバイソン(野牛)だと分かる。発見したのが、少女だということも納得できる。大人では、目と絵の距離が近すぎ、見つけられないだろう。でもこれが、1万年以前の絵だと信じるのは難しい。
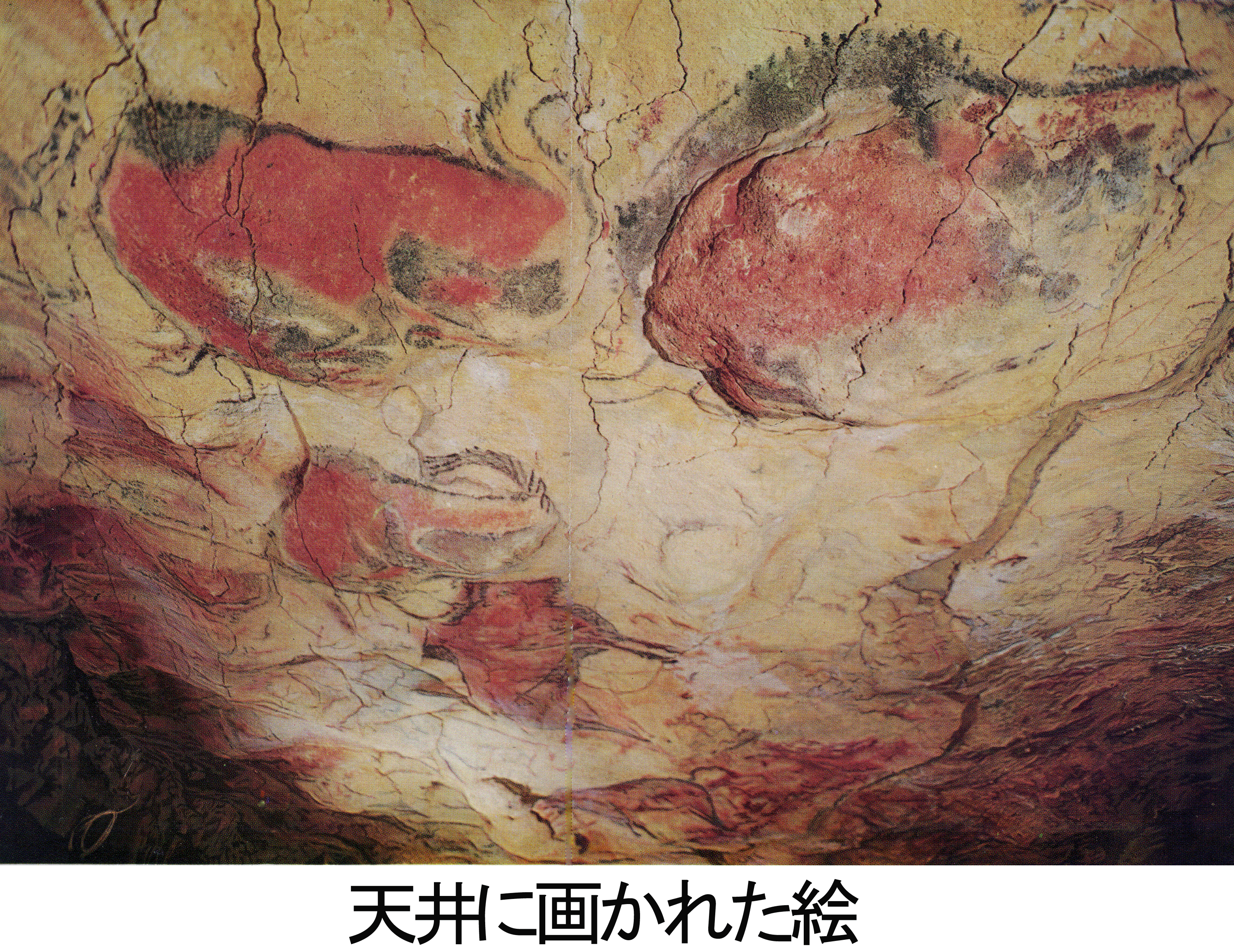

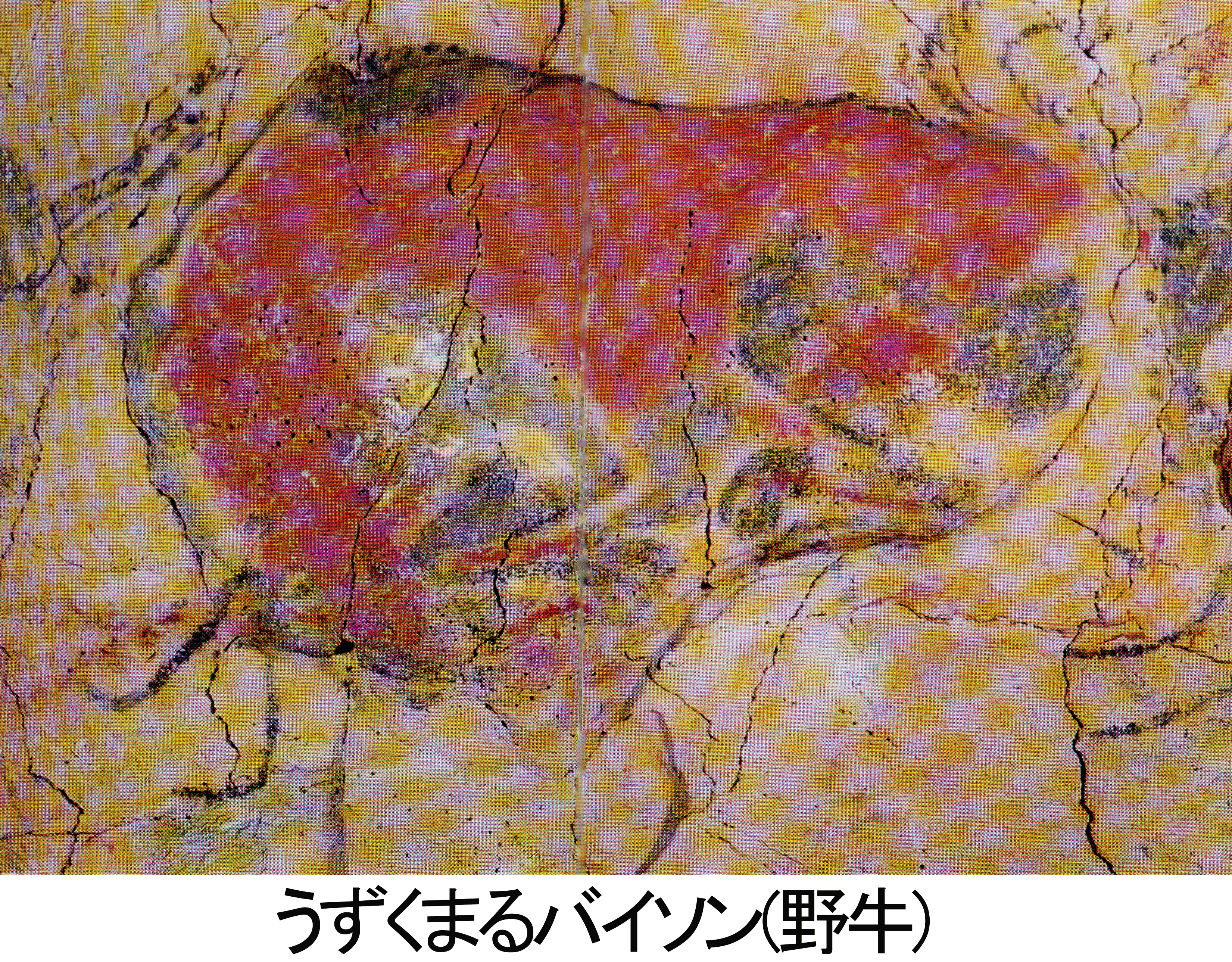
ミケランジェロが天井に絵を描いたローマの教会に因んで、「先史時代のシスティーナ礼拝堂」とも名付けられているが、現在は公開されていない。1万年近くも封鎖されていた洞窟が外気に触れて痛みがひどくなったためである。実物は、たしかに、絵だと思えたが、画かれた時代については見当がつかない。当時もいろいろな議論があって、アルタミラの壁画が旧石器時代のものと信じられるようになるためには20〜30年ほど必要だったらしい。アルタミラのあと、フランスのラスコー遺跡が発見されたことから、本物と認定されたらしい。さらに今ではスペイン北部で14の洞窟でも壁画が見つかっている。



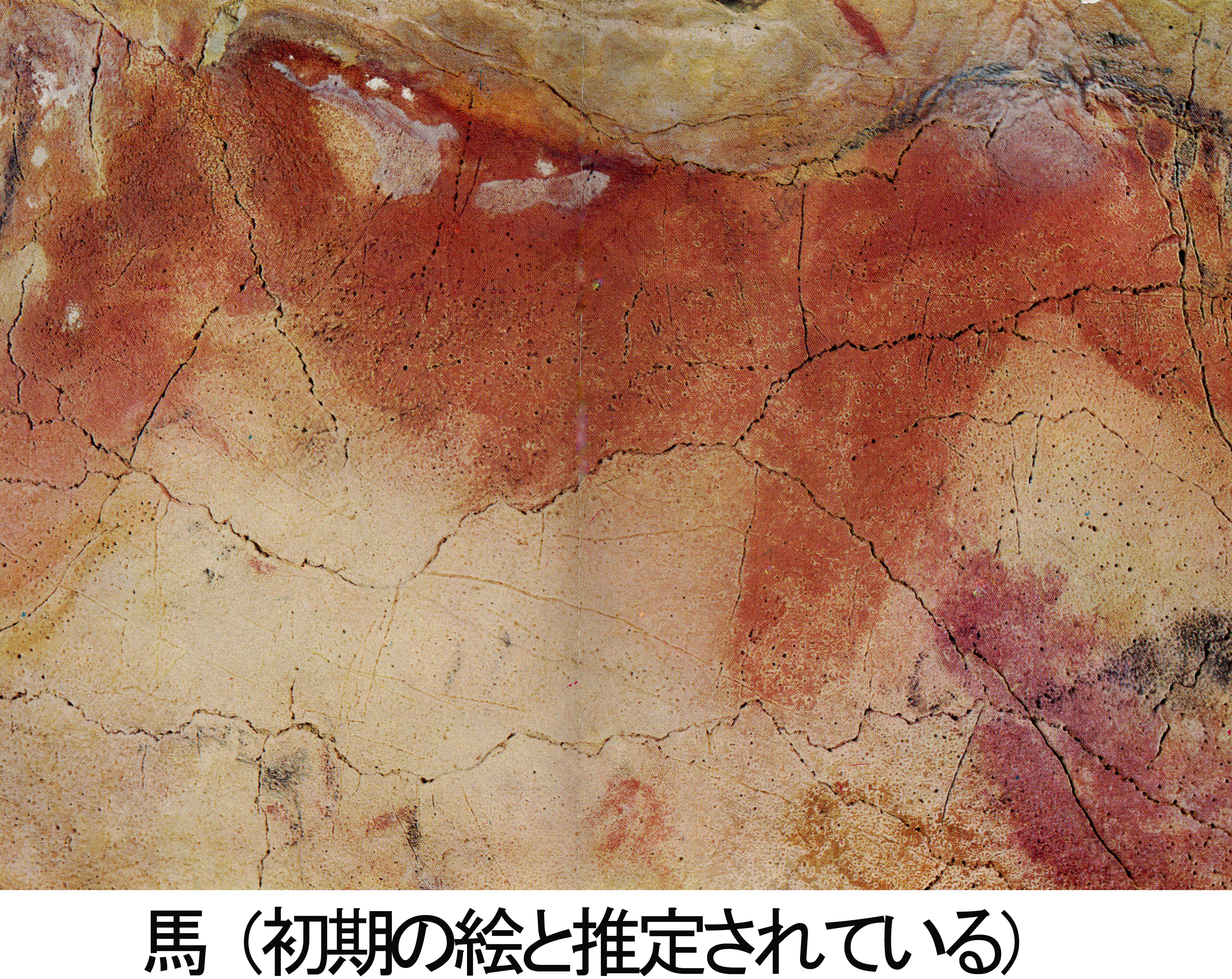
バルセローナ
バルセローナはスペインの北東に位置し、地中海に面する都市である。ローマ起源の町、中世に地中海を制覇した都市国家、フランコ政権に反抗した街、カタルーニャ州の首都、スペイン第2の都市、都市計画の街等々、一言ではまとめられない町である。1974年に展示会があって、行くことになった。
バルセロナと書くのが普通だが、現地の発音に合わせてバルセローナとした。
1974.9.27 バルセローナ
スペインのバルセローナに着いた。二日後に日本から本隊が来るので、それまでに準備しなければと意気込んだが、肝心の展示物が到着していない。あちこち尋ねて廻る。日本に問い合わせる。予定通り発送したそうだが、物がスペインまでたどり着いているかどうかも不明。焦るが、どうしようもない。

バルセローナの地図を見ると、都市発展の跡がはっきり分かる。ローマの遺跡の上に立つゴシック地区、旧市街、19世紀末の拡張市街と広がっていくのが見える。旧市街も実はランブラス大通り(城壁の跡)を挟んで、右左別々の町だったらしい。19世紀に拡張された地区は、頑強な都市計画によるもので、これだけの整然とした区画を持つ都市は欧州では珍しい。19世紀後半にヨーロッパで都市改造の流行りがあり、パリ、ウイーンもその跡が残っている。


1974.9.30
展示小間を空っぽのまま、開ける。
夜、やけのやんぱちで、パエリヤを食べにいった。出てきた鍋を見た瞬間、上司から「なんで、こんな残飯を食わなければならないのか」と怒鳴られた。しかし、なんと言っても本場のパエリヤだし、私の好物でもあるのだが・・・。

パエリャの発祥はバレンシアだが、バルセローナでも代表的な米料理である。サフランの黄金色が特徴。
1974.10.2
知り合いの、アメリカから来た教授が夕食に招待してくれたが、ちょっと心配だった。と云うのは、昨晩、魚料理を食べに行ったが、問題が起きた。ブイヤベースのような、魚介鍋である。大きな魚は輪切りにして、小さな魚やエビ類はその姿のままで、大盛りにして一緒に煮込んだ料理だが、山のように魚介類が盛り上げられた鍋が出てくると、一瞬ぎょっとする。こんな「死骸累々」は食べられるかと誰かがつぶやいた。しかし名物料理である。ひょっとすると、今晩の招待にも出てくるかも知れない。なんとなく、魚料理は苦手と伝えたつもりだったが、やっぱり魚の鍋料理が出てきた。日本人全員元気が無くなった。どうもスペイン(カタロニア州)料理は日本人には合わないようだ。
多分、スケットと呼ぶ鍋料理だと思うが、地中海のありとあらゆる魚介類のごった煮で、小エビ、車エビ、ムール貝と一緒にメルルーサのような大きな魚の輪切り、名も知らない小魚はそのまま、本当に山盛りで出てくると、たしかにうんざりする。フランスのブイヤベースより野蛮な(あるいは素朴な)料理であった。映像を探したが、残っていない。小粒だが、似たような魚介鍋の写真をウエブから拝借した。

1974.10.3
市庁舎でパーティ。このあたりはバリオ・ゴティコという、古い地区らしい。
バリオ・ゴティコ(ゴシック・クオーター)はランブラス大通りの裏にある(いや大通りが城壁だったので、本来は、この位置が表である)。ここはローマの植民都市の上に立てられ、中世では都心であった。大聖堂など古い建物が残っていたはずだが、記憶に残っていない。
1974.10.5
仕事は終わった。スペイン村(Poble Espanyol)に行く。町の南のモンジュイクの丘の上にある。いかにもスペインらしい建物が並び、スペインの民芸品を作り、即売している。みやげとして、帆船模型、フラメンコ人形、ケープなどを買い込む。


スペイン村は、1929年のバルセローナ万博の時に、スペインを紹介するために建てられた小さなテーマパークである。スペイン西部のガリシア地方、西北部のバスク地方、東部のカタロニア地方、南部のアンダルシア地方そして中央のカスティリヤ地方のそれぞれの代表的な建造物のコピーが作られている。そして建物の中で工芸品を作り、販売している。現在でも健在らしい。スペイン特有の輝くような白い建物で一杯だったが、所詮イミテーションである。スペインのあちこちで現物を見る機会があったから、今となっては、サグラダ・ファミリヤやピカソ美術館などへ行った方がよかったと思うが、後の祭り。モンジュイクの丘から、遠くサグラダ・ファミリヤの尖塔だけが見えた。土産物は、最近まであったはずだが、いつからか見つからなくなった。


夜、数人でランブラス大通りをうろつく。バルセローナきっての繁華街である。ワインを飲み、フラメンコをやっているタブラオを覗き、酔って大通りを闊歩する。いい気分であった。いろいろあったバルセローナもこれでお終い。


旧市街のランブラス大通りは昔の城壁の跡らしいが、道の中央に街路樹が並び、両側には見世物屋や飲み屋がひしめいている。タブラオでは、たばこの煙と舞台から立ち上る埃で、視界が遮られる中、フラメンコの音が響いている。踊りに飽き、酔ってワイン片手に、街路樹に寄りかかり、街の喧噪を眺めては、悦に入っていた。
